2014年に神奈川県から小千谷市の岩沢集落に移住して早10年が経ち、11年目に突入しました、せいのうれいと申します。
栄養学を学び、食品メーカーの研究所勤務を経験し、はたまたNGOのボランティアとしてケニアで子供の支援に関わったり、そのほかにも介護職や事務職や飲食業や、あれやこれやと職を転々としてここにたどり着きました。
現在の本業は(何が本業か分からないのですが、中でも自分が事業主として行っているものは)【ポレポレ工房】という菓子製造業ということになりますでしょうか。お米や地元の素材を生かしたお菓子、オーダーケーキ、時にお弁当やお惣菜なども作っています。

また、成り行きで始めた農的暮らしにすっかり魅了され、畑や田んぼで土と戯れる、いわゆる【半農半X】的な生活も板についてきて、最近では『本業は農家ですか?』とまで聞かれるようになりました。(笑)
実際のところポレポレ工房以外にも、農業法人のお手伝いや受託の事務仕事などいくつかの収入源を持ちつつ、本業も暮らしも楽しむイナカフリーランスです。
そんな私も気が付いたら移住から10年、とうとう町内会の【会計】という役を担うことになり運営に関わるようになりました。
移住前は知らなかったこの地域の組織について、この2年間で経験したことや考えたことをまとめたいと思います。
町内会という組織とその役割
私が現在住んでいるのは、小千谷市の岩沢という地域です。岩沢は、住居表示でいうところの『大字』です。
昔は岩沢村という村だったそうです。明治時代、町村性施行に伴い中魚沼郡『岩沢村』が誕生しました。
1955年(昭和30年)に小千谷市に編入され、岩沢村は『大字』となったのだそうです。
令和7年2月現在、231世帯(令和7年2月現在)が住んでいます。
その岩沢には、住居表示には使われていませんが行政区としての10の【町】があります。
そして町内ごとに、生活インフラの維持や行事などが行われているのです。
私の住む『山谷(やまや)』町内は64世帯で構成されています。
基本的に、住民になったらその町内に町内会費を納める必要があります。金額はそれぞれの町内で違うのですが、人口が少ないエリアほど高く、多いほど安いという傾向があります。
過疎化の進む地方は、【人口が少ない=税収が少ない➡行政サービスが十分に行き届かない】だから町内会という自治組織を作って、生活を維持するための活動が必要になる、ということのようです。
私の町内は月3,600円ですが、小千谷市内でも住宅地のエリアだと500円というところもあり、岩沢の件数の少ない町内では5,000円のところもあります。
町内の編成としては、町内の中でさらに数件ずつが『隣組』という、いわゆる班みたいなものに分かれています。この隣組が最小の単位となり、配り物や小さな行事などを一緒に行うことになります。
移住当初から、住民として参加してきた活動は以下のようになります。
●年3回の『道普請(みちぶしん)』
町内の清掃、美化活動です。というとごみ拾いのようなことを想像するかもしれませんが、ここのような山に面した地域では道路沿いの枝を刈ったり、草を刈ったり、大量に落ちてきた落ち葉を片づけたり、側溝のごみを取り除いたり、あとは神社の整備(草取りなど)などになります。春、夏、秋に1回ずつ、年3回あります。各戸から必ず1名は参加することになっており、参加できない場合は『出不足料』として3,000円を払う決まりになっています。

●集会所の清掃
毎月1回、隣組単位で行います。今月は1組が行ったから来月は2組の皆さんよろしく、という具合に順番が回ってきたら行います。回ってくるのは年に1回ぐらいでしょうか。
●消雪パイプの手入れ
雪国なので、冬には消雪パイプが活躍します。これも町内で管理しているものになるのですが、手入れが必要なのです。たとえば水の出口が詰まったり、水の出る量が多すぎたり少なすぎたりとなることがあるので、雪の降らない時期に、点検と調整を行います。これも隣組で行っています。

●風祭り、秋祭り
各町内には必ず神社があり、その神社で行うお祭りです。五穀豊穣を願う、れっきととした神事ですが、レクリエーションとしても大事な地域の行事です。強制参加ではありませんが、高齢の方やお子さんのいるご家庭など実際楽しみにしている方も多いのです。
風祭は7月に、秋祭りは8月末に行われます。この町内会では風祭りはどちらかというと小ぢんまりと役員を中心に神社に集まって行われ、秋祭りはお神輿で町内を回ったり、ビンゴゲームで景品が当たったりと盛大に行われます。
ちなみに秋祭りの協賛金として全世帯2,000円を徴収されます。

●賽の神(さいのかみ)
小正月(1月15日)に行われる行事です。正月飾りなどを藁と共に燃やして無病息災を祈るものとのことです。地域によっては『どんど焼き』とも呼ばれ、この煙にあたるのは縁起が良いとされています。この火でスルメを吊るして焼くのが昔からの風習のようです。

地域行事への参加は、移住当初は『けっこう大変だなあ…』とは思っていたのですが、考えてみればこのような共同活動を通じて近所の方々とのコミュニケーションが深まるのですね。そうして皆さんと仲良くなると、何となく安心するところは確かにあるのです。助け合いの精神のようなものが自然と生まれる感じがします。
そして年度末には、隣組での慰労会も行われます。『今年もお疲れさまでした』という会ですね。
町内会費の使い道
さて、もちろん『町内会費』というものにも移住前は無縁でした。当初よく分からないけど【決まりになっているのだから払わないわけにいかないお金】という認識です。当時は、隣組長さん(これも順番で回ってくる役割)が毎月回収に来て現金で納めていましたが、何年か前から口座引き落としになりました。
その集めたお金、何に使われているのか?
初めは全く分かりませんでしたが、だいぶそのあたりも分かってきました。
ざっと説明させていただきますと・・・
●共有施設の維持費
集会所や神社、町内の街路灯、ゴミ置き場などの維持費です。具体的には電気代やガス代、保険料、固定資産税、借地料などに充てられます。
●子供会、消防団、老人会への助成
地域にはこれらの団体も存在するので、活動費として町内から助成しています。
●敬老会の費用
この辺りでは毎年敬老の日の前後、75歳以上の方を招いて盛大な宴が行われます。役員が企画して高齢者の皆さんをもてなし、楽しんでいただく席です。このための飲食費、写真撮影、お土産代などです。ちなみに我が町内、昨年の敬老会参加者はだいたい30名ほどでしょうか。
●役員手当、会議費など
役員になると毎月集まって委員会を開き、活動についての話合いなどが行われます。また様々な町内活動の企画運営を行わなければなりません。はやり一番大変なのは会長ですね。市からのお呼びで平日に会議に出なければならないこともかなりあるようです。会社勤めなどがある方は、わざわざ休みを取ったりもしているようです。
私の町内の場合、以下のような役職があります。
町内会長、副会長、会計、文書配布係、道路委員、管財委員、農家組合長、防除班長、書記。です。
捕捉しますと、道路委員は道路の整備の担当、管財委員は祭事担当です。農家組合長とか、防除班長とか、ちょっとよくわからないですよね。農業者の皆さんの組織なのですがなぜか町内会と一体化しています。その昔、合理化する意味でこのような形になり、それが今も続いているのです。
とりあえずこんな風になっています。文書配布係というのもなかなか大変で、田舎というのはなぜか配り物や回覧文書がとても多いのです(いいか悪いかは別として)。
また会議費は、委員の人たちの飲食費です。1年間頑張っていろいろな活動をしているのだから、時に慰労会などで労をねぎらうことが認められています。
●各種負担金
これは、全世帯が納めることになっているもので、各種協議会などの維持のために負担するお金です。具体的には、交通安全協会、地元小学校中学校の後援会、振興協議会、社会福祉協議会、住民センター維持、林道委員会、防犯連絡協議会、観光協会、消防施設地代、公民館活動費などです。令和6年度の場合1戸当たりの負担額はそれぞれですが100円~1,500円となっており合計すると年間で8,300円となります。ずいぶんいろいろあります。
この辺りもまあ、なんというか、見直すべきところは多々ありそうだなと個人的には思うところです。
●消雪パイプの維持費
積雪時、道路に水を流します。そのためにはポンプを動かす電気代がかかります。維持費は主にこの電気代に当てられますが、使っているとやはり修理や、部品の交換が必要になってきます。費用はかかっていますが、冬場の生活はこれにとても助けられています。
町内費の使い道としては、ざっとこんなところになります。
また、収入としては私たちの納める町内会費のほかに、市からの行政事務手数料、敬老会補助金、活動費の助成金などがあります。行政も手が回らない分お金を回してくれているのですね。
この辺りまでが分かってくると、だいぶ町内会の何たるかが想像できてくると思います。とはいえ私自身も、役員になるまでは決算書などまじめに見たことがなかったというのが事実です。
会計のお仕事。町内会向けの会計ソフト。
会計ですから、もちろんお金の管理をするのが任務です。
町内会費は口座引き落としですが、残高不足で引き落とせないケースが時々あります。その場合は本人にお知らせして現金で回収します。
あとは、何かにつけて買い出しに行くのも会計の役割でした。集会所のトイレットペーパーがないから買っておくとか、役員で慰労会をするから飲み物とか食べ物を買いに行くとか、お金の出入りが伴うことはだいたい会計の仕事になります。
あとは、人にお金を配る仕事。
町内として使っている土地(ゴミ置き場や消雪パイプの井戸)の借地料、役員手当てなどなど各個人にお金を配る必要があります。これもなかなか手間のかかる仕事でした。あっちこっちにお金持って行って、領収のサインもらって、ということをします。
そしてやはり年度終わりの決算書の作成…
引継ぎ時にはエクセルで出納帳をつけて集計していたのですが、この集計作業がまあ面倒くさい、というのが1年目で感じたことでした。
2年目に入ったとき、クラウドの良いソフトがないかと(しかも無料の)探してみたわけです。そうしたら、あったのです。
その名も【ちまたの会計】
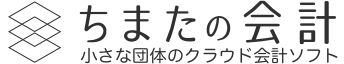
あらかじめ科目の設定をして記帳しておけば、台帳の作成や科目別の集計は自動です。
これは助かります!!グラフなんかも作ってくれちゃいます(必要ないけど)。
読者のみなさま、団体の会計を担った際にはどうぞ使ってみてください。
そして無事に総会も終わり、2年間の会計の任務から解放されました。本当に、ほっとしました。
役員も、どうせやるなら仲良く楽しく。
町内会という組織がないと、この地域での人々の生活の維持は難しいのだなということはよく分かりました。
合理化・簡略化はやろうと思えばできるところはあると思います。ただ、中に入ってみて感じることは、昔からの慣習を変えることもなかなかの苦労が伴うということです。何か小さなことでも住民の皆さんの同意が必要であり、意見が出たらそこに対応しなければなりません。大きな声で反対を叫ぶ人がいたらそこに太刀打ちするにはかなりのエネルギーも必要です。確かにそれは大変だろうなと…

この2年間で、さらにこの地域を深く知ることが出来たのはよかったです。そして恵まれたことに、役員メンバー総勢12名の皆さんが良い人だったことです。
町内会長はじめ50代位(この辺りでは若手になる)が多く、気さくで話しやすい人ばかり。おかげでいつも和気あいあいと楽しい空気の中、様々な任務をこなすことができました。今まであまり接点のなかった人とも顔を合わせて話す機会が格段に増えたので、より一層仲良くなれました。
また保守的になり過ぎず、変えていくべきという考えを持つ人も多かったので秋祭りにおいては以前よりもだいぶ規模縮小、簡略化をして行いました。住民の皆さんの現状、役員の負担などを鑑みてもこれは良かったと思います。
それでいて、地域に対する愛情は持っていて『みんなが喜ぶように』とか『最低限保つべきところ』などはちゃんと考えられており、【よそ者】の私からするとそこはさすがだと感じました。
年度末の大仕事【総会】が終わって、役員のみんなで慰労会です。いやいやお疲れさまでした!!

そしてその時の会話、『役員は終わったけど、またこのメンバーで飲み会やりたいね~。来年また集まろう。』
なんて話も出るくらい。
町内会というのは、強制加入ではなく最近は入らなくても良い地域もあるようですね。それはそれでありだと思います。ただこの地域ではそれはなかなか難しいのが事実です。
思うところも気苦労もいろいろあるけれど、これからも住み続けるのなら仲良くした方が良いし楽しい方が良いに決まってます。ざっくばらんに話ができる関係づくり。それがあってこそ今後の展望も開けてくるものだと感じました。
せいのうれい 半農半X型イナカフリーランス
2014年地域おこし協力隊として移住。任期終了後にポレポレ工房を起業、地元の食材や自家栽培の素材などを使ったお菓子や料理の製造販売を行う傍ら、農業法人でのアルバイト受託仕事やをしながら生計を立てている。なりゆきで畑や田んぼをあてがわれてから野菜や米作りに魅了され、趣味と実益を兼ねて農作業にいそしむ。










